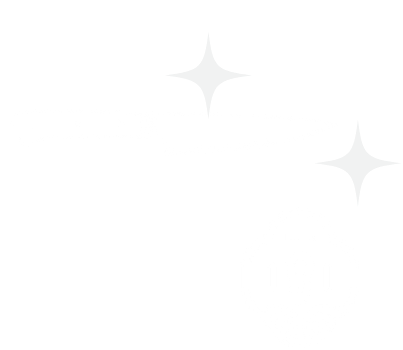食材にこだわる飲食店が増えた今、料理人が行き着くのが包丁へのこだわり。 包丁の質や手入れの行き届いた店は例外なく美味しい。
「味でつなぐ 料理人探訪」は、グルメサイトのレーティングでは伝えきれない、本当に美味しい店を紹介するシリーズ。
包丁から見えてくる技術、哲学、そして食へのまなざし。 料理人の内面に踏み込み、本質を探る。
第12回目は、天満にある日本料理「雲鶴」。
“大阪料理”の特徴である、鮮度の良い海・山・里の食材にこだわり、「始末の心」を表現する一方、食材の研究者としての一面を持つ店主、島村 雅晴氏にお話を伺った。